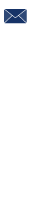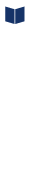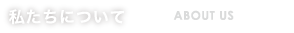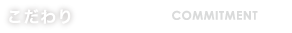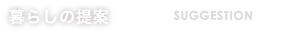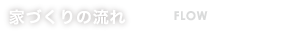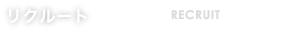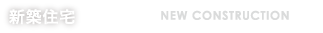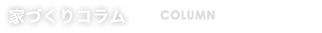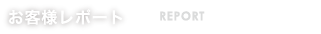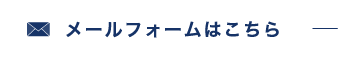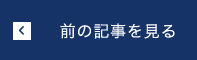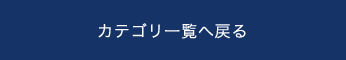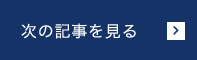室内の“温度格差”をなくす家づくり〜断熱と気流の基礎知識〜
2025.09.08
家づくりのお役立ちコラム
「リビングは快適なのに、廊下やトイレは寒くてつらい」「同じ部屋なのに、足元だけ冷える」──こうした“室内の温度差”は、日本の住宅に多く見られる課題の一つです。実際、冬場のヒートショック事故などもこの温度差が大きな要因といわれています。
快適な室温を保つためには、冷暖房の強化だけでなく、家そのものの「断熱性能」と「気流のコントロール」が重要です。この2つをうまく設計に取り入れることで、年間を通して快適に過ごせる住まいを実現できます。
今回は、そんな“温度格差のない家づくり”のために知っておきたい基本の考え方をわかりやすくご紹介します。
「断熱」の考え方と重要性
室温を保つために欠かせないのが断熱性能。これは「外の暑さ寒さを、どれだけ室内に伝えにくくするか」という住宅の基本性能のひとつです。
・断熱材と気密の関係
断熱とは単に“冷たい空気を入れない”ということではありません。断熱材の性能と同時に、その周囲の「気密性」も重要です。すき間風や漏気があれば、せっかくの断熱材の効果も半減してしまいます。断熱=密閉、ではありませんが、「断熱材+気密処理」のバランスこそが効果を最大化します。
・部位ごとの断熱強化が効果的
壁・天井だけでなく、足元からの冷えを防ぐ「床断熱」や、熱の出入りが多い「窓まわり」の断熱対策も忘れずに。近年では、樹脂サッシやLow-E複層ガラスなどの高性能な窓が一般化しており、省エネにも貢献しています。
・断熱は“暮らしのコスト”にも影響
断熱性が高い住まいは、冷暖房効率が上がり、年間の光熱費を抑える効果も期待できます。一時的な投資に見えて、長期的には大きな安心と経済性をもたらしてくれるのです。
空気の“流れ”をデザインする
もう一つ注目したいのが、室内の空気の流れ、つまり気流の設計です。断熱で守られた空間でも、空気がよどんでいたり流れが偏っていると快適さが損なわれます。
・自然な空気の“めぐり”を意識する
近年の住宅は高気密化が進んでいるため、計画換気や自然通風の設計が重要になります。給気口・排気口の位置を考慮することで、各部屋に新鮮な空気がめぐり、湿気や汚れも溜まりにくくなります。
・空気の層をかき混ぜる“サーキュレーション
暖かい空気は上に、冷たい空気は下に溜まる性質があります。そこで、天井扇(シーリングファン)やサーキュレーターなどを併用し、空気の上下を緩やかに混ぜる工夫も有効です。
・間取りがつくる空気の道
家の中を移動する動線だけでなく、“空気が通る道”も間取りの重要な要素。廊下の幅、ドアの開閉方向、小窓やスリットの配置など、ちょっとした配慮が温度ムラを防ぐ助けになります。
まとめ:心地よさは目に見えない設計から
住宅の快適性とは、デザインや広さだけでは測れない部分にこそあります。特に「温度差のない空間」は、住む人の健康やストレスの軽減、さらには省エネ性能にも大きく関わる要素です。
これから家づくりを考える方には、断熱性能や空気の流れといった“目に見えない設計の工夫”にもしっかり目を向けていただきたいと思います。それがきっと、長く快適に暮らすための確かな基盤になるはずです。